2022年度GAPシンポジウムは、好評のうちに終了しました。ご参加くださりありがとうございました。
2022年度GAPシンポジウム ストリーミング配信のご案内
一般社団法人日本生産者GAP協会では、去る2023年2月9~10日に開催されました「2022年度GAPシンポジウム」における講演につきまして、参加者限定で各講演をストリーミングにてご視聴いただけます。
ストリーミング配信の視聴ご希望の方は、ご視聴までの流れをご覧の上、お申し込みください。
事前にお申し込み済みの方も、引き続き、下記の期間までご視聴いただけます。
視聴可能期間 配信開始2月16日(木) または 参加登録時 ~ 2022年3月31日(金)23:59
※オンデマンド配信は、好きな時間に何度でもコンテンツの視聴・閲覧が可能です。
※資料のダウンロード、視聴の権利は、お申込者様ご本人のみとなります。視聴URL、パスワードは厳重に管理してください。
開催趣旨
2022年度シンポジウム テーマ
『みどりの食料システム戦略』と『適正農業管理(GAP)』
EUの「Farm to Fork戦略」、アメリカの「農業イノベーションアジェンダ」に続き、日本でも「みどりの食料システム戦略」が策定され、その実現のために「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」が公布されました。大きな農業・食料システム戦略の変革(トランスフォーメーション)に向けて、サステナブル・エシカル消費とそれに応える農業技術と農場管理(GAP)について、専門家の知見や現場の取組みを学びます。
開催概要
- 名称
- 2022年度 GAPシンポジウム
- 会期
- 2023年2月9日(木) 受付12:00~開始13:00~17:00
10日(金) 受付9:15~開始9:45~17:00 - 会場
- 【ハイブリッド開催】
オンライン(Zoomウェビナー) ・ つくば研修支援センター(会場定員 50名)
※開催後に参加者限定で各講演のビデオをストリーミング配信 - 参加費
- (個人)主催・共催の会員:\7,500、一般:\11,250、大学生: \1,500、高校生:無料
(団体:農学系大学・専修学校・農業高校の授業として聴講):\11,250 - 主催
- 一般社団法人日本生産者GAP協会
- 事務局
- 一般社団法人日本生産者GAP協会 教育・広報委員会、株式会社AGIC大会事務局
- 共催
- 農業情報学会
一般社団法人GAP普及推進機構
特定非営利活動法人経済人コー円卓会議日本委員会
一般社団法人沖縄トランスフォーメーション(沖縄DX) - 特別協賛
- 株式会社つくば分析センター
プログラム
※講演内容、時間は進行上の都合により変更になる場合もございます。あらかじめご了承願います。(敬称略) 1月20日更新
2月9日(木)
| 12:00~13:00 | 受付 |
| 13:00~13:15 | 開会・オリエンテーション |
| 13:15~14:00 | 講演 政策のパラダイムシフト「みどりの食料システム戦略」 EUの Farm to Fork 戦略に学び GAPステージの周回遅れを取り戻す 田上隆一 一般社団法人日本生産者GAP協会 理事長 |
| 14:05~14:50 | 講演 エシカル消費に応える持続可能な農業 山口真奈美 一般社団法人日本サステナブル・ラベル協会 代表理事 |
| 14:55~15:40 | 講演 持続可能な農業の次のステップに向けたGLOBALGAPver6対応 田上隆多 株式会社AGIC 事業部長 |
| 16:00~16:45 | 総合討論 田上隆一、山口真奈美、田上隆多 |
| 16:45~17:00 | 1日目クロージング |
2月10日(金)
| 9:15~ 9:45 | 受付(入室) |
| 9:45~10:00 | 2日目オリエンテーション |
| 10:00~10:45 | 講演 日本農業のトランスフォーメーションを考える DX×SDGsとGAP 中島洋 一般社団法人沖縄トランスフォーメーション 代表理事 一般社団法人日本生産者GAP協会 理事 |
| 10:50~11:35 | 講演 米国農業のパラダイムシフト「健全な土壌のための生態学的管理」 山田正美 一般社団法人日本生産者GAP協会 専務理事 |
| 11:40~12:00 | 質疑応答 |
| 12:00~13:00 | 昼休憩 |
| 13:00~13:45 | 講演 窒素循環の再生で持続可能な農業生産へ 小川吉雄 元茨城県農業総合センター 園芸研究所長 |
| 13:50~14:35 | 講演 「本物の野菜作り」から学ぶ総合的作物管理(ICM)の実践 髙橋広樹 株式会社みずほアグリサポート |
| 14:40~15:25 | 講演 GLOBALGAP認証を通した持続可能な農業に向けた教育体制の構築 ~GLOBALGAPの日常的な実践を目指す~ 鳴川勝 和歌山県農林大学校 |
| 15:25~15:40 | 休憩 |
| 15:40~16:45 | 総合討論 質疑応答・総合討議 |
| 16:45~17:00 | クロージング・閉会 |
講演
①政策のパラダイムシフト「みどりの食料システム戦略」
EUの Farm to Fork 戦略に学び GAPステージの周回遅れを取り戻す
田上隆一
一般社団法人日本生産者GAP協会 理事長

農林水産省の「みどりの食料システム戦略」が、EU共通農業政策の「Farm to Fork戦略」を参考にしているということなので、EU委員会からEU議会、EU理事会等に提出された「公正で健康的かつ環境に優しい食品システムのためのFarm to Fork戦略」の原本を読んでみました。戦略の基本や達成の目標がほぼ同じであれば、そこから「みどりの食料システム戦略」の本質が理解できるかもしれません。
講演
②エシカル消費に応える持続可能な農業
山口真奈美
一般社団法人日本サステナブル・ラベル協会 代表理事

GAPは持続可能(サステナブル)で倫理的(エシカル)な方法で農業を営むことです。今、世界の消費行動基準は、原料の生産や調達から消費に至る全ての過程においてサステナブル・エシカルであることが求められています。エシカル消費の意義や情勢をひも解くことで、サステナブル・エシカル生産である持続可能な農業(GAP)の重要性・必要性について理解を深めます。
講演
③持続可能な農業の次のステップに向けたGLOBALGAPver6対応
田上隆多
株式会社AGIC 事業部長

農産物取引シーンでグローバルに展開する総合農場保証(IFA)制度「GLOBALGAP」は、EU共通農業政策の「Farm to Fork戦略」など、持続可能な農業・食料戦略の大転換の方向を反映し、2015年のメジャー改定以来、7年ぶりにバージョン改定が行われました。気候変動、エネルギー、炭素貯留に関する追加や、土壌健全性のための土壌管理計画の強化など、農場における実践レベルでの変更点と今後の取組みのポイントなどについて学びます。
講演
④日本農業のトランスフォーメーションを考える DX×SDGsとGAP
中島洋
一般社団法人沖縄トランスフォーメーション 代表理事
一般社団法人日本生産者GAP協会 理事

GAP規範の中の農薬や化学肥料の使用を減らす目標はSDGsの「気候変動への対策」や「生物多様性の維持」に相応します。GAPは実は、農業の「エシカル生産」実践の指針なのです。SDGsを物差しに現状の農業を見直し、消費者が意識する「エシカル消費」につなげることで、農業のトランスフォーメーションに踏み出せる可能性があります。
講演
⑤米国農業のパラダイムシフト「健全な土壌のための生態学的管理」
山田正美
一般社団法人日本生産者GAP協会 専務理事

米国では、農業の環境フットプリントを半減させるという目標を掲げ「農業イノベーションアジェンダ」を発表しています。米国農務省の持続的農業研究教育プログラムでは、地球温暖化防止の視点も取り入れた「より良い作物のための土づくり」という体系的な指導書を発行しました。農業の問題は、これまでの対処療法よりも有機物の蓄積と維持に重点を置いた適切な土壌管理によって、すべて解決されるか少なくとも軽減することができる、という基本的考え方で貫かれています。
講演
⑥窒素循環の再生で持続可能な農業生産へ
小川吉雄
元茨城県農業総合センター 園芸研究所長
環境と調和を図りながら農業生産を持続的に維持発展させるには、土壌を環境資源として位置づけ、有機物を利用した土づくりと、土壌診断、栄養診断に基づいた適正な施肥管理、地域を中心として輪作体系の確立を一つのシステムとして構築することが必要です。農地からの硝酸態窒素の流出機構の解析から、持続可能な農業生産技術に向けた窒素循環の再生を目指した土壌・施肥管理技術について学びます。
講演
⑦「本物の野菜作り」から学ぶ総合的作物管理(ICM)の実践
髙橋広樹
株式会社みずほアグリサポート

「土作り」と「施肥」、「防除」と「IPM」のようにそれぞれを別の技術体系として捉えるのではなく、作物生体を、土壌管理、作物養分管理、病害虫管理が互いに関連した技術体系として管理することが、結果として環境的にも経済的にも社会的に持続可能な農業生産に繋がります。農業現場での「本物の野菜作り」指導の事例を通して、持続可能な農業の技術的中核をなす総合的作物管理(ICM)について学びます。
講演
⑧GLOBALGAP認証を通した持続可能な農業に向けた教育体制の構築
~GLOBALGAPの日常的な実践を目指す~
鳴川勝
和歌山県農林大学校
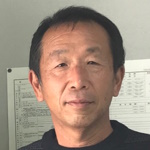
次代の農業者や農業関連産業従事者を育成する農林大学校の農場運営は、持続可能で適正な実践でなければなりません。和歌山県農林大学校では3カ年をかけて全校(全コース)でGLOBALGAP認証(果樹、野菜)・MPS認証(花卉)に取り組みました。学生の自主的な気付きと成長と同時に、教育を提供する教員側の認識と体制の改革に取り組んだ経緯から、これからの農業教育のヒントについて学びます。
ご視聴までの流れ
- お申込み
- ① 参加ご希望の方は、申込みフォームにてお申込みいただくか、参加申込書へ必要事項をご記入の上、EmailはたはFAXでお申し込みください。(届いたFAX用紙をもとに事務局でフォームの入力を代行いたします)
② フォームの登録が完了いたしますと、ストリーミング視聴のご案内をしている限定ページへのアクセスに必要となる「ログインID」と「パスワード」を、参加登録時にご入力いただいたメールアドレスへお送りいたします。 - ご視聴方法
- 限定ページより、視聴する講演の映像をクリックし、ご案内したパスワードを入力してください。
講演資料(スライド等)は、同ページよりダウンロードができます。ストリーミング配信の視聴時にご覧ください。配信期限まで、繰り返しのご視聴・閲覧いただけます。ストリーミング動画は、編集が完了次第、2月16日から公開いたします。
ご視聴が終わりましたら、ご案内ページにございますアンケートにご協力ください。
- お支払方法
- 参加費は、お振込みとなります。お申し込み時のご記入に従い、ご請求書を発行いたします。
1講義のみの受講でも参加費は同じです。IDとパスワードを含む このメールをもちまして、ご請求が発生いたしますこと、ご了承くださいませ。 - 宛先
メール mj(アットマーク)fagap.or.jp FAX 029-856-0024 - 参加費(資料代)
主催・共催会員 ¥7,500(税込) 一般 ¥11,250(税込) 学生 ¥1,500(税込) 高校生 無料 農学系大学・専修学校・農業高校の授業として聴講
※農学系大学・専修学校・農業高校の授業枠参加専用のお申込み用紙がございます。詳しくは事務局にお問い合わせください。\11,250(税込) - 取扱口座
振込先銀行 三井住友銀行 つくば支店 口座番号 普通預金 0152070 口座名義人 イツパンシヤダンホウジンニホンセイサンシヤギヤツプキヨウカイ
一般社団法人日本生産者GAP協会
- お問い合わせ
一般社団法人日本生産者GAP協会
TEL : 029-861-4900
FAX : 029-856-0024
Email:mj(アットマーク)fagap.or.jp